
鹿とは、4つ足の草食動物で日本全土に生息しています。特に奈良県は有名ですね。
ここでは、鹿の特徴を少し変わった角度で、角、寿命、種類、危険度、漢字の5つを紹介していきます。
鹿の新たな一面を垣間見て、会話の小ネタとして活用してくれたらうれしいです。
角の役割
鹿の角は枝角(アントラー)と呼ばれ、性的ディスプレイやオス同士の争いの武器として使われます。メスは生えません。ちなみにみんなご存じチョッパーのモデルのトナカイはメスでも生えます。
角(アントラー)は 毎年生え変わる「骨」 が本体で、牛やヤギの角(ホーン)は一生伸び続けて骨の芯を覆う角鞘で、鹿の「アントラー」とは根本的に構造が違います。これが「鹿だけが毎年角を落とす」理由になります。
生え変わった枝角は毎年枝分かれの数が増えていきます。この個数を見ればある程度年齢も把握でき、動物園での個体管理に役立ちます。
角(アントラー)には神経が通っていません。主な成分はケラチン、コラーゲン、カルシウム、インスリン様成長因子などで皮膚が変化したものです。爪や髪の毛と同じ成分なので角を切られても痛くはありません。ヒトでいう爪切る感覚です。
あくまで完成した角では痛くありませんが、成長途中の袋角と呼ばれる時期(春から夏)はやわらかい状態で成長し、神経も通っているので痛いです。飼育員時代に鹿友達に触らせてもらいましたけど、ホッカイロくらいあったかいです。
成長するとオスは木の幹やフェンスに角をこすりつけて外側の袋を破きます。その後も角研ぎを行い、立派な角に仕上げてきます。ですが、飼育下では木が痛んだり、フェンスを壊されたり悩みの種です。
寿命ってどのくらい?
野生のニホンジカの平均寿命は4歳程度で、1歳未満で半数が死亡するといわれています。飼育下ではオスで15歳、メスで20歳程度まで生きることがあります。野生寿命が短いのは捕食や冬の飢餓も大きな要因。
ですが、飼育下でもここまで生き残るのはとても少ないです。私がいたところの死亡原因の多くは、オス同士の争いで角が体に刺さり傷ついて衰弱死するパターンでした。成長したオスは力も強いので一撃でも致命傷になります。
飼育下での「オス同士の争い」は確かに深刻で、動物園では 繁殖期だけ隔離する 施設も多いです。
そのため、飼育下のオスは除角をする場合もあります。奈良公園の鹿も安全性を考え鹿の角切りを伝統行事として行っています。
種類はどのくらい?
日本に生息する鹿は、主に「ニホンジカ」という種類で地域によって呼び方が変わります。亜種といい、7種類があげられます。
- 北海道:エゾシカ
- 本州:ホンシュウジカ
- 四国・九州:キュウシュウジカ
- 対馬:ツシマジカ
- 屋久島:ヤクシカ
- 馬毛島:マゲジカ
- 慶良間諸島:ケラマジカ
世界には約16属36種以上のシカが生息しており、トナカイ、ヘラジカ、アカシカ、ワピチなどがあげられます。
奈良のシカは、奈良公園周辺に生息している野生動物のニホンジカになります。国の天然記念物に指定され、春日大社の神の使い「神鹿」として大切にされています。
鹿の危険度
草食動物は、基本的には穏やかな性格をしており、危険性は低く見られてしまいがちです。ですが、条件次第では肉食獣よりも危険なので気を付けましょう。
鹿が餌を目の前にして頭を上下する行動があります。お辞儀しているような動きですが、実はイライラしているサインです。その後、首を背中側にそらして歯をぎりぎりさせてくると、キレる一歩手前。
犬とは違い、従順ではないのでお預けはできません。餌があれば全力で食べに来るので、餌を与えるときはさっと出してさっとあげましょう。
突然しゃがむ行動も気を付けましょう。鹿の基本攻撃は前足によるものなので、鹿の目の前でしゃがむとびっくりして前足でたたかれます。爪も結構鋭いので、ひっかき傷ができてしまいます。
発情期(9月から11月)の時期のオスにも注意しましょう。前述しましたが、角による闘争がありますので巻き込まれると大惨事になります。たとえ角がなくても突進力はかなりのものなのでオスには近寄らないのが吉。
一番気を付けるのが、子供がいる母鹿です。鹿はハイダーと呼ばれ、子供を茂みに隠し親は離れて行動します。このとき不用意に子供に近づくと、母鹿が毛を逆立て警戒し、前足を地団太を踏むようして警告し、その後攻撃行動に移ります。
この時の母鹿は相手がどんなものでも攻撃してきます。自分より大きくて固い車にも突進してきます。母の愛を感じる部分ですが、子供には極力近づかないようにしましょう。
海外にワピチという大型のシカがいるのですが、私がいた飼育現場で「大人のワピチは熊を殺す、ワピチには近づくな」というように教わりました。
漢字から学ぼう
象形文字で、角のある鹿の姿をかたどったものです。画数は11画で小学4年生の時に習います。
鹿を使った変わった言葉は、
- 馴鹿(じゅんろく):トナカイを指す漢字で、昔から穏やかな動物と認識されている
- 麤(そ):粗い、荒々しい、煽る、粗末などが主な意味で、現代日本語ではほぼ使われない。
- 鹿驚(かかし):獣肉などを焼いて串にさし、その匂いをかがせることで鳥獣をお求めたことから「かがし」と呼ばれ、それがかかしになった説がある。
ちなみに馬鹿という言葉は、鹿を馬と強引に言い張る姿勢が、ものの本質を見抜けないさまを象徴するようになり「馬鹿」と書かれるようになりました。
うまをしかにとおす:権威をかさに着て、筋の通らぬことをむりを承知で押しつけることをいう。中国で、権力に野心を燃やす秦(しん)の趙高(ちょうこう)が、謀反(むほん)を企てたさい、臣下が自分につくかどうかを試そうと考え、時の幼帝に鹿を馬と称して献上した。幼帝がこれは馬でなく鹿であろうと臣下に尋ねると、臣下のなかのある者は黙して答えなかったが、趙高にへつらう者たちは、いや馬であると答えた。だが、幼帝に忠誠を誓い、正直に鹿だと答えた臣下は、趙高によってひそかに厳罰に処せられ、それ以後、人々をふるえあがらせたという故事による。
引用:会話で使えることわざ辞典https://imidas.jp/proverb/detail/X-02-C-03-7-0007.html
まとめ
今回は、鹿の角、寿命、種類、危険度、漢字に着目して解説してみました。
角の正体
鹿の角は「アントラー」と呼ばれ、骨でできています。ウシやヤギの角(ホーン)は一生伸び続けますが、鹿は毎年生え変わるのが特徴。成長期の「袋角」には血管と神経が通っていて温かく敏感ですが、硬化して完成すると神経はなくなり、切っても痛みはありません。
寿命のギャップ
野生のニホンジカは平均4年ほどと短命。飼育下ではオス15年、メス20年ほど生きることもありますが、オス同士の角による争いで致命傷を負うケースも多く見られます。
鹿の種類
日本にいるのはすべて「ニホンジカ」の仲間。地域ごとに分かれた7亜種(エゾシカ、ツシマジカ、ヤクシカなど)が存在します。世界には約36種類の鹿がいて、トナカイやヘラジカもその仲間です。
草食=安全ではない
鹿は穏やかそうに見えますが、繁殖期のオスや子を守る母鹿は非常に攻撃的になります。頭を上下させる「お辞儀」のような動きは、実はイライラのサイン。前足の蹴りや突進は人にとっても危険です。
文化と鹿
奈良公園の鹿は「神の使い」として守られてきました。漢字「鹿」は象形文字が起源で、「馬鹿」という言葉にも鹿が関係しています。古くから人の文化や言葉に深く関わってきた動物です。
鹿はかわいい反面、野生という過酷な環境で生きるための仕様がいくつも装備されています。角のサイクルや行動パターンを知ると、観察がもっと面白く、安全にもつながります。
ぜひ、奈良などで鹿に近づくときは今のことを思い出して、いい思い出をつくってもらいたいです。
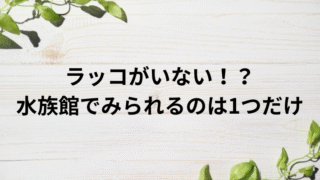
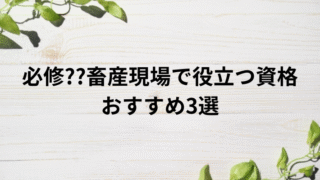
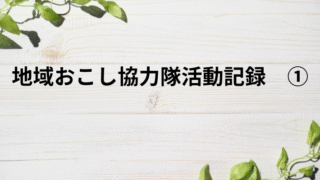
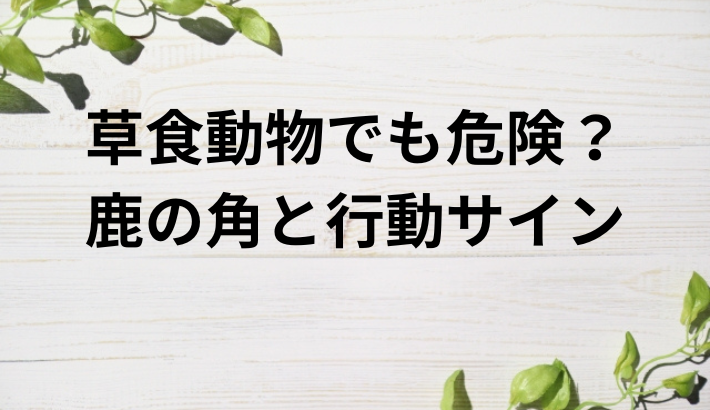

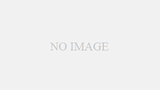
コメント