ネットのニュースで「太陽光発電と羊放牧は完璧な組み合わせ」ソーラーグレージングで一石三鳥。っていうのがあった。
太陽光発電は太陽の光を電気に変えるシステムだけど、その天敵になるのが日光を遮る植物。それを羊に食べてもらい、肉として出荷、出した糞は土壌の肥沃にもつながるので一石三鳥である。とのこと
果たして本当にうまくいくものだろうか。私が思いつく課題を出してみよう。
- 羊が食べる植物を太陽光発電施設で確保できるのか
- 人間が思った通りのところを除草してくれるのか
- 羊が出荷できるまで成長させることはできるのか
- 放牧のみで肉質は問題ないか
- 羊の管理はどうするのか
この辺りが一石三鳥を実現させるために必要な課題かな。
まず、羊はやわらかい新芽部分を好んで食べます。かたい茎や長く伸びた草は残すことが多いです。さらに嫌いな草は絶対食べません。果たして、太陽光発電を実施しているところで羊がすべて食べてくれる草を準備できるものでしょうか。
羊の牧草地で使われているのは主に、イタリアンライグラス、チモシー、オーチャードグラス、アルファルファなどです。種をまいても太陽光パネルの日陰部分できちんと育つのか。疑問なところ。
植生をまったく気にせず、いわゆる「雑草」をそのまま与えるとします。その場合は食べないところの箇所を対策しないといけない点。つまりは太陽光パネルの近くに背の高く羊が食べない植物が生えていた場合、人間が刈るしかなくなるということ。羊だって食べる植物、食べない植物があります。それを無理やり訓練して全ての植物を食べさせるのは現実的に不可能。
さらには、放牧のみ、雑草のみで出荷できるまでの羊が出来上がるのかという点。羊の出荷にはラム、ホゲット、マトンがあります。それぞれ生後1年未満、1年から2年未満、2年以上という区分になります。まずラムですが、放牧のみで出荷体重までもっていくのは難しい。この中で当てはまりそうなのは放牧しながら長年飼って出荷するマトンが当てはまると思われます。これなら太陽光施設での放牧も理にかなっています。
さて、果たしてその肉はどうなるでしょうか。一般に放牧中心で育った羊は香りが強くなる傾向があります。原因として言われているのは
- 食べた植物が反芻胃植物が反芻胃内で分解されてでる臭気物質
- 羊肉の脂は不飽和を多く含み、酸化しやすく不快の原因になりやすい
- 年齢が上がった成羊は臭みが強く出やすい
羊肉が避けられる理由は、「臭いが強い」というのがあげられます。「太陽光施設で育てた羊肉だけど臭いは強いです」今の日本でこれが受け入れられるときは来るのでしょうか。羊肉が多く普及するようになってくれればいいんですが。
最後に、太陽光施設に羊を入れればそれで終わりなのか。やはり生き物である以上管理は必要です。水の交換、脱走の有無、健康状態の確認、補助飼料の給餌、柵の破損確認などは毎日やる必要があると思います。これやるくらいなら、月一くらいで草刈りしたほうが楽なんじゃないかと思います。完全放置はダメ、絶対。
まとめ
太陽光発電×羊放牧の組み合わせを考えてみました。一見「一石三鳥」に見えるが、課題は多くあります。
羊は柔らかい草を好み、雑草を完全に除草するのは難しい。太陽光パネル下では牧草の生育も不安定で、放牧のみで出荷体重に達するのも困難。さらに放牧羊は肉の香りが強く、市場性にも課題が残る。水や健康管理、柵の点検など日常管理も不可欠で、結局は人手が要る。現状では「放っておくだけで除草と肉生産ができる」ほど簡単な仕組みではない。というのが私の見解です。
これはアメリカでの記事なので、仮に日本に置き換えて考えたら、難しいんじゃないかという話です。なんでこんなことを考えたかというと
太陽光発電だけではなく、耕作放棄地でも同じことが言えるかなと思ったからです。草ぼうぼうのところに羊を放したところできれいにはならないということ。人間の管理はやっぱり必要。だから羊と人間が一緒に管理するのが最適解になるのかもしれません。
今後耕作放棄地を使うことがあるかもしれません。その時に調べたことが役に立てばいいなと思ってマガジン風にまとめてみました。
では、では。
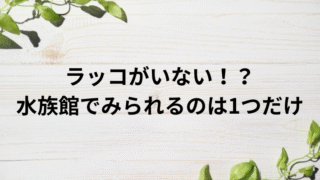
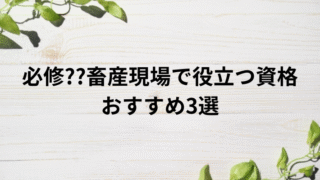
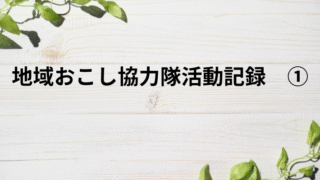
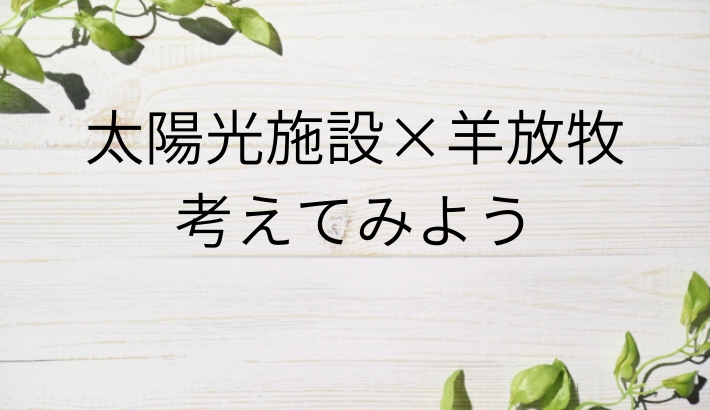
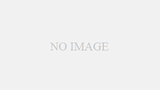
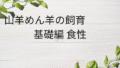
コメント